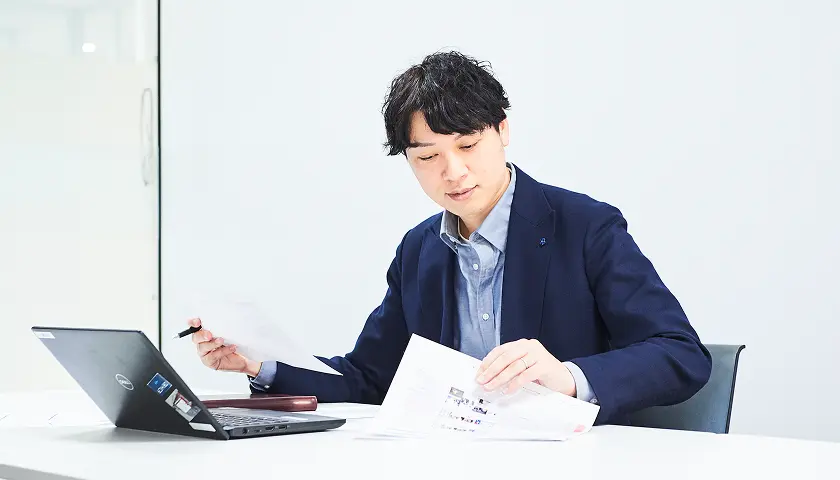店舗の売上を
ECサイトに奪われる
というジレンマを超えて
佐分:ORIHICA全体の販売チャネルがデジタルにシフトする中で、店舗スタッフのスタイリング写真を投稿してはどうかという提案が出てきました。スタッフスナップを展開する他社では売上の拡張に成功している、という情報も得ていたのです。ORIHICAはというと、コロナ禍以前だったこともあり実店舗とECサイトの相互補完という考え方はまだ薄かった印象がありました。ECサイトに売り上げを取られたくない、1円でも多くの売上を店舗で確保したいと考えるのは無理もありません。こうした意識をいかに変えていくか。人事部の営業教育担当として、新たな考え方を店舗スタッフに浸透させていくことが私の役割でした。
なにしろ0から1を生み出す業務のため、軌道に乗せるまでは苦労の連続でした。先行してスタッフスナップに取り組んでいるトライアルメンバーの販売実績と社内認知度を、同時に高めていく必要があったのです。まずは販売スタッフに理解してもらうべく働き掛けたのですが、「店舗の業務だけで精一杯」「お客さまとの直接の触れ合いを大切にしたい」といった消極的な声が多くを占めていました。
それでも私は悲観していませんでした。なぜなら導入して間もなく、トライアルメンバーたちが楽しんでいることがひしひしと伝わってきたからです。「仕事なのに趣味のように面白い」という若手スタッフや「新鮮な体験で入社1年目を思い出した」というベテランスタッフもいました。そうした反応を見ているうちに、実店舗でもウェブでも接客の本質は変わらないんだという確信を得ていきます。こんなにイキイキとしているスタッフたちの様子をもっと知ってもらいたいーー。トライアルメンバーの情報を定期的に上層部やエリアマネジャーたち、もちろん現場にもしっかり伝えることを心掛けていきました。